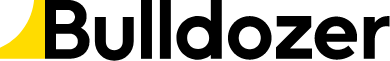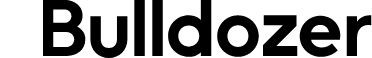Interview インタビュー
イノベーション
IT・ソフトウェア







オリジンを問い、“自分じゃなくてもいい仕事”から”自分だからやりたい誇れる仕事”に
パナソニック システムデザイン株式会社様

POINT1 アート思考に出会い“自分の仕事の意味”を問い直したことが、個人の挑戦の後押しに
POINT2 社外での挑戦を社内に還元する地道な草の根活動が組織に変化を起こす
POINT3 問いを立て自分の視点を持つことで”子供に誇れる活動を自ら創り出す”
「社内に”挑戦するカルチャー”を広めていきたい」
「新しい時代に新しい価値を生み出したい」
「与えられた仕事だけで満足していいのか?」
という想いを持っておられる経営層及び管理職の方々や社員の方々に読んでいただきたい記事です。
変化の渦の中で、大企業であっても今までの様に安泰とはいかない現代において、社内外を超えて自ら挑戦・行動できる人材がどれだけいるか、またそうした社内カルチャーがあるかは、非常に重要なポイントになります。本記事は、パナソニック システムデザイン株式会社でシステムエンジニアとしてご活躍されていてアート思考を実践されている明石太陽氏に、アート思考を学ぶ前の自身の仕事への葛藤、学んだ後の思考の変化、その後の挑戦についてインタビューを行いました。
◾️パナソニック システムデザイン株式会社
パナソニックが提供するシステムのソフトウェア設計・開発を行っている。中でも、家電・住空間事業、モビリティ事業、BtoBソリューション事業を主軸に新しい商品やサービスの創造に取り組んでいる。
◾️概要・実施背景
コロナ禍で先行きの不透明な中、正解を生み出し、既存事業や新規事業においてイノベーションを生み出す人材育成やカルチャー醸成として、アート思考プログラムを実施。3段階に分かれており、1段階目は部門内でのプログラム、2段階目は選抜制イノベーション人材育成プログラム、3段階目にアート思考を体現するブルドーザー留学プログラムを実施。
◾️インタビュー参加者
明石太陽氏
同社でシステムエンジニアとしてキャッシュレス決済端末の設計・開発に従事。その傍ら社内外の様々な有志活動のコミュニティに参画している。中でも、起業家育成プログラムや女性活躍推進コミュニティの事務局としても活動中。
<組織のカルチャー変革に関する活動>
2020年 高度デザインブリッジスクール(現:DXDキャンプ)0期生/ Panasonic 社内起業家育成プログラム BOOST CONTEST 1期生&事務局/ 大企業挑戦者支援プログラム CHANGE by ONE JAPAN 3期生&事務局/ 経済産業省・JETRO 主催「始動 Next Innovator 2022」 8期生/Panasonic Game Changer Catapult 8期生/経済産業省主催 起業家育成・海外派遣プログラム「J-STARX」 シリコンバレー派遣/ 株式会社ユニコーンファーム主催 スタートアップ大学(SUU) Batch2/ 特許庁主催 スタートアップとプロボノのマッチングプログラム「スタボノ」
アート思考導入のきっかけ ー「自分でなくてもできる仕事」への危機感
自分でなければ創り出せない価値を探し求めて

尾和:当時どのような経緯でアート思考やブルドーザーに興味を持ってくださったのですか?
明石氏(以下、明石):私はシステムエンジニアという職種ですが、この職種ではQCD(品質・コスト・納期)を決められた時間内で、いかに効率的に作るかということが絶対的な価値です。私も「決められた通りに実現する」ことが絶対的な価値だと思っていました。その一方で、「言われたものを、より早く正確に作るだけの人」でこのまま大丈夫なのだろうか、と不安に感じる時期があったのを覚えています。「自分でなければできない価値」という視点が必要だと思ったんです。その視点が無ければ、作る人は別に自分でなくても良いとなれば、海外へのオフショア開発にシフトしていくことも十分に考えられますよね。
尾和:2010年代は中国経済が急成長し、様々なものがオフショア開発され、製造業の強い日本には何が残るのかって議論になっていましたよね。それは日本だけでなくて他の先進国でもそのような議論が出ていました。当時、色々な葛藤を抱え未来について様々な情報収集をしていらっしゃったと思うのですが、どうしてその中でもアート思考に可能性を感じてくださったのですか?
デザイン思考のその先を問う「アート思考」
明石:アート思考とよく一緒に出てくる考え方で、「デザイン思考」がありますよね。デザイン思考は、当時もよく聞く言葉で業界にも入ってきていました。 デザイン思考の講座も色々と行きましたが、デザイン思考の先を行くのが「アート思考」ということも言われていました。デザイン思考は、「ユーザーを起点とした課題を解く」という前提が根底にありますよね。エンジニアの多くは「動くものを作ること」に関心が向いている方が多いので、「このシステムは、なんでこの世の中に必要なんだったっけ?」みたいなところってあまり深く意識してないケースが多いように感じていました。ですが、根本の目的を外さないようにしたいという思いがあって。だから、アート思考的な問いかけ、つまり当たり前を疑う視点を取り入れる必要性を感じ、Bulldozerさんのところに行きました。あの時は、今の三越前のオフィスでも、前の表参道のオフィス「Gravity」でもなくて、松濤のオフィスでしたよね。
尾和:そうですね!(笑)創業してから間もない時でしたね。あの時は今よりもっとアートよりでしたね。作品作り、立体作品っていうのをやってましたよね。オリジンにフォーカスしていたからなんですよね。
明石氏:やってました、やってました。手を使って、ものづくりをしてましたよね。
ブルドーザー留学で0→1を実地で経験。自分でなければ創り出せない価値の片鱗を。

明石:Bulldozer留学では、週に1日Bulldozerさんで事業の実践をさせてもらいました。最初に2日くらいワークショップを受けました。もともと個人的な興味だったのですが、業務時間内で挑戦できることがあるなら、それを活用したいなって思って。当時の上司に相談したら、「社員が新しいことに挑戦する文化を根付かせたい」と言っていただけて、行かせてもらうことになりました。それから、組織としても「1人で行くより、他のメンバーも一緒に行ったほうが、社内にカルチャー変革の想いが浸透するんじゃないか」という話になって他の方も誘いました。
尾和:学ぶ機会は多くても実践できる機会がないと血肉になりませんよね。
明石:そうですね。座学の講義を受けても、結局それって“知識”でしかないと思うんです。実践しないと身につかないし、体験が伴わないとすぐ忘れるので実践をしようと思いました。
尾和:自転車の漕ぎ方を聞いても、乗れないと意味ないのと一緒ですよね(笑)
明石:講義で「いい話聞いたなぁ」と思っても、いざやってみたら全然できないということはよくあります(笑)
尾和:太陽さんたちと共に取り組んだ、東急グループ創始者・五島慶太翁の偉人の追体験プログラムは、非常に満足度の高いプログラムとなり、Bulldozerにとっても大きな転機となりました。慶太翁が生きた時代背景や育った環境にも深く触れ、そこから得たインサイトをもとに「才能を最大化するとは何か」を探求し、参加した皆さんが才能を最大化するためのプログラムへと、アイデアを形にしていきました。
これをきっかけに、”追体験シリーズ”が生まれ、2023年の秋には本田技研工業様のドイツ・フランクフルト開発拠点にて、本田宗一郎氏の追体験ワークショップを実施することができ、こちらも組織変革にあたって高評価をいただくことができました。
明石:そうだったんですね。確かに、日本には素敵な創業者が多いので、多くの企業がオリジンに立ち戻るために、唯一無二の方法かもしれませんね。追体験のプロジェクトでは、五島氏の故郷である長野県青木村を実際に訪れ、現地でのリサーチや未来創造館の皆さまへのインタビューを行いながら開発を進めましたよね。0→1で何かに取り組むことがとても面白かったです!
尾和:一緒にブルドーザー留学に来た他の方の変化について何か感じることはありましたか?
明石:一緒に行った方も毎日仕事をする中で、心のどこかで「これって本当に自分がやりたかったことなんだっけ?」って、当時はモヤモヤしていたのではないかと思います。でも、Bulldozerのアート思考のワークショップや、事業の実践の経験は、それを考え直すいいきっかけになったと思います。特に若い世代だと、「与えられたことは全部やります。それが社会人として当然です」っていう気持ちが強いじゃないですか。だけど、「私はほんとにこれがしたくてこの会社に入ったんだっけ?」って立ち止まる瞬間があったんじゃないかなと思います。その方は、データ分析をやりたいと言っていて、今はやりたいことに近づけてると思います。
社外での経験と社内への還元で広がる視野と組織の可能性
社外での経験やネットワークがキャリアだけでなく“人生の財産”に
尾和:プログラム参加後、様々な取り組みをされて才能が爆発していらっしゃいましたよね!どんなことをされましたか?
明石:「Panasonic 社内起業家育成プログラム BOOST CONTEST」や、「大企業挑戦者支援プログラム CHANGE by ONE JAPAN」、「経済産業省・JETRO主催 イノベーターを育成する “始動 Next Innovator”」、「Panasonic Game Changer Catapult」、「起業家育成・海外派遣プログラム “J-STARX”」など色々なことに参画してきました。
尾和:太陽さんはパナソニックグループだけでなく、経済産業省の起業家プログラムや大企業挑戦者支援プログラムの事務局サポートをされていますが、何が醍醐味だと感じていますか?
明石:社外のプログラムに参加するというのは、長い目で見た時のキャリアや人脈作りという意味で、大きなモチベーションです。2018年ぐらいから比べると、一緒に活動する人の幅は圧倒的に広がったと思いますね。2018年は、自社の中で動いているだけで、関わる人と言えば同じ部署の人たちだけだったように思います。社外の方との繋がりはキャリアだけに留まらず、人生においてもすごい財産だと思いますね。尾和さんとの出会いもその中の一つです。
外に出ると会社の中で体験することとは全然違う世界が見えるので、最近はそれを社内にできるだけ還元しようとしています。当時、そういう取り組みが会社であまり良く捉えられないのではないかという不安があり、ほとんど情報を発信することはありませんでした。
尾和:発信して還元されているとのこと、素晴らしいですね。広い視野を持って、皆のために還元してくれる人って有難い存在だと思います。実際にどのように風に還元してるんですか?
明石:例えば、事務局をさせていただいているパナソニックグループ横断有志コミュニティのTeamsや社内チャネルでは、外で学んだことを発信したり、機会を紹介したりしています。社内の人に社外の人を紹介するということもかなり増えています。外に目を向けるきっかけの1つとして、会社の役に立っていたら嬉しいです。「個々の挑戦から組織としての挑戦」に広げるような活動は絶対に必要だと思います。

尾和:今聞いてて思い浮かんだイメージなのですが、仕事以外の時間に太陽さんが村から出て、色々な食べ物の実を調達してきて、種を植えてこっそり水撒いて、実がなった時に、「この果物美味しいんだよ!食べてみて!」みたいな。なんかそういう感じなのかなと思いました!(笑)
明石:そうですかね(笑)いきなり「みんな外行こうぜ」って言っても誰も来ないから、まずは1人で行ってみて、「美味しそうなものがあるからちょっと取ってきたんだけど、今度は一緒に行ってみない?」みたいな(笑)外で実績を作って社内に展開すると皆さん興味を持ってくれます。
尾和:なるほど。草の根活動ですね。かなり時間がかかりませんか?
明石:社内のカルチャー、マインドセット変革は時間がかかると思いますし、一人では到底できませんから、まずは自分にできることから地道に発信しています。周りの人をどうやって巻き込んでいくかみたいなところは結構重要だと思います。
尾和:会社の上層部の方や、総務、人事の方から、社員の皆さんが危機感を持って変わっていくにはどうすれば良いかという相談を受けるのですが、危機感を持つ、もしくは「会社を変えていくのは楽しいかも!」って思ってもらうためにはどうしたら良いんですかね。

明石:私のようなサラリーマンは、危機感を持たなくてもお給料をいただけるので、現在の業務以外のことに進んで取り組む必要性はほとんどないですよね。言われてもいない新しいことに挑戦しても、それが評価に繋がる可能性も低いですし、挑戦して上手くいくことの方が少ないですし。また、失敗に目がいってしまうと、周りに良い印象も与えないですよね。「失敗しないように行動する」といった日本特有の風潮もあるじゃないですか。だから無理して挑戦しないのかなと思います。
尾和:確かに。でもその中で、太陽さんは、 危機感を持って会社を変えようとしていらっしゃる。やっぱり会社がどうあるべきかや、どういう価値を生み出すかというところに対して、自分のオリジンと会社のオリジンを重ね合わせながらその方向性を決めていくということが大切だと思うんです。この時代、一般的に、多くの企業の経営層も自社の未来の方向性について迷っているように感じます。ボトムアップで考えてもらおうと、お題が降りてくるのですが、部長が分からないと課長に、課長が分からないと現場に、というようにみんなが分からない状態なんです。どの階層の人も「自社がどうありたいのか」「何のためにこの事業をしているのか?」という問いを自分たちの側から持てるようになることが重要だと思います。
「どうすればできるか?」に思考が変化
明石:冒頭でお話ししたように、エンジニアの多くは決められた要件をいかに正確・高速に実装するかに集中し、「実際にどう使われているのか?」や「そもそもなんで存在するのか?」という問いを意識しないケースが多いように思います。その点で、 アート思考は、その問いを常に引き起こす視点を与えてくれました。
他には、日々のタスクや会議で「どうすればできるか?」に思考を切り替えることが増えましたね。時間がないという言い訳をするのではなく、どうすればその時間を捻出できるかといった、観点を変える意識が出てくるので働き方の面でも良い影響を与えてくれたと思っています。
尾和:ここが結構、企業文化や組織風土のドライバーな気がします。どうしたらできるか?というその言葉が出てくるかですよね。「Yes, and」でしたっけ?
明石:そうです。起業家シリコンバレー派遣プログラム「始動 Next Innovator」やシリコンバレー現地では「Yes, and」がとても大切なマインドセットとして教えられています。相手に対して否定をせず、実現しなさそうな挑戦もまずは肯定します。無理かもしれないことでも、できるようにするためには、現状のどこを改善すべきか?という思考ですね。また、やること/やらないことの判断軸もクリアになりました。オリジンに従って優先順位を決めています。自分じゃなきゃできないことに多くの時間を使うようになりました。
尾和:自分のオリジンを深く知り、アイデンティティがはっきりすると、判断軸も見えてきますよね
明石:そうですよね。大きな組織の中にいると、決められたことをそのままやるという働き方になりがちなので、どうしたらここをパラダイムシフトさせられるかを自分で考えることが大切ですね。決められたことを決められた通りにやるのは基本です。ただ、少なくとも経営や企画、新規事業を生み出す人たちには絶対にその考え方が必要ですよね。

自分と会社のオリジンに基づく新しい挑戦の価値
尾和:太陽さんのようにしっかりと自分のオリジンを見つけて、会社のオリジンとも重ね合わせて、その上で新しい挑戦をし、新しい価値を生み出していくことってすごく大事だと思います。そういう想いを、大企業の方たちにどう伝えたら刺さると思いますか?
明石:過去の成功事例を気にする大企業の方々に刺さるようにするには、やっぱり「数字や実績として示す」のが一番早いと思いますが、正直こういう領域って短期的な数字では出ないんですよね。
尾和:無理やり出そうとすると、なんかうさんくさく見えますよね。
明石:カルチャー変革は、すぐに結果が出るものではないと思いますし、根気強く長期的な目線で取り組んでいかなければいけないと感じています。しかもアート思考みたいなものは、「どこにどう効いてるのか」が目に見えにくいです。ロジカル思考やデザイン思考とも通じますが、最初はアウトプットとの繋がりが見えにくいと思います。でも、体感では効いているんですよね。 こういった活動は、緊急ではないがとても重要なものとして、取り組む価値を提示していくしかないですよね。全員がすごくイノベーティブである必要はないと思いますが、次の時代を生き抜くために、新しい事業を創ろうとされている人は少なからずいるので、その人たちにまずは刺さればいいんじゃないかなと思います。
自身の仕事観への影響ー仕事に対する誇り
「作る人」から「創り出す人」へ。子供に誇れる仕事を
尾和:そんなイノベーションのコアになる人たちに、アート思考をおすすめする一言をお願いできますか?
明石:自分も含めて、「作る人」じゃなくて「創り出せる人」になっていこうと思います。エンジニアリングの領域でものを作る人って世の中に沢山いますが「それって何のために存在してるんだろう?」って考える人は、それほど多くはないのではないかと思います。AI活用も積極的に進んでいますが、AIが得意なのは“業務効率化”の方です。でも「そもそもなんでそれが必要なの?」って問いを立てたり、本質を考えることはまだ人間にしかできない。
だから、これからの時代は「効率化の先にある価値を創り出せる人」が求められると思うんです。そういう意味で、「作る人」じゃなくて「創り出せる人」になる。そんなマインドが大切だと思います。アート思考を取り入れて一番良かったことは、子供たちに対して、「お父さんはこういう活動をしているんだよ」って自信を持って言えるようになったことです。今、誇れる活動をしていると思います。「お父さんは新しい未来を作ってるんだよ」みたいなことまで言えるとさらにかっこいい気がしますよね。
尾和:今のすごく良い言葉ですね。「誇れる仕事」。
明石:だから挑戦を認めてくれたり、評価する制度があればより良いと思います。仲間も応援してくれると嬉しいですね。決まった業務を遂行するのは当たり前で、それに加えて会社の目指す方向性と整合性のある取り組みで付加価値を生み出した場合に、評価へ反映される仕組みがあれば、挑戦する人がもっと増えるかもしれませんね。

尾和:人事部の皆さんとも、ぜひ一緒に考えていきたいですね!太陽さんのお話を伺い、改めて感じたのは、個人の挑戦が組織へと還元され、組織として新たな価値を生み出すことの大切さです。それぞれの取り組みが会社の目指す方向性と繋がり、そこから新しい価値が生まれていく。そこには時間をかけて草の根で育てていく力が求められますが、太陽さんが実践し、成果を上げておられることは、クライアント企業の風土改革やマインドセット改革に取り組む私たちBulldozerにとっても大きな励みになっています。
このインタビューが、「挑戦したい!」「会社を変えていきたい」と考えている方々にとって、新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば嬉しいです!太陽さん、素敵なエピソードをご共有してくださり、本当にありがとうございました。
他企業様の事例をみる
Contact
資料のダウンロード・
お問い合わせはこちらへ
「アート思考、良さそうだけどピンときてない・・・」「うちの組織にどう適用したらいいかわからない」
そう思うのは自然なことです。どんなことでもお気軽にご相談ください。