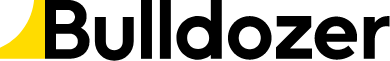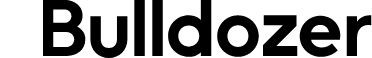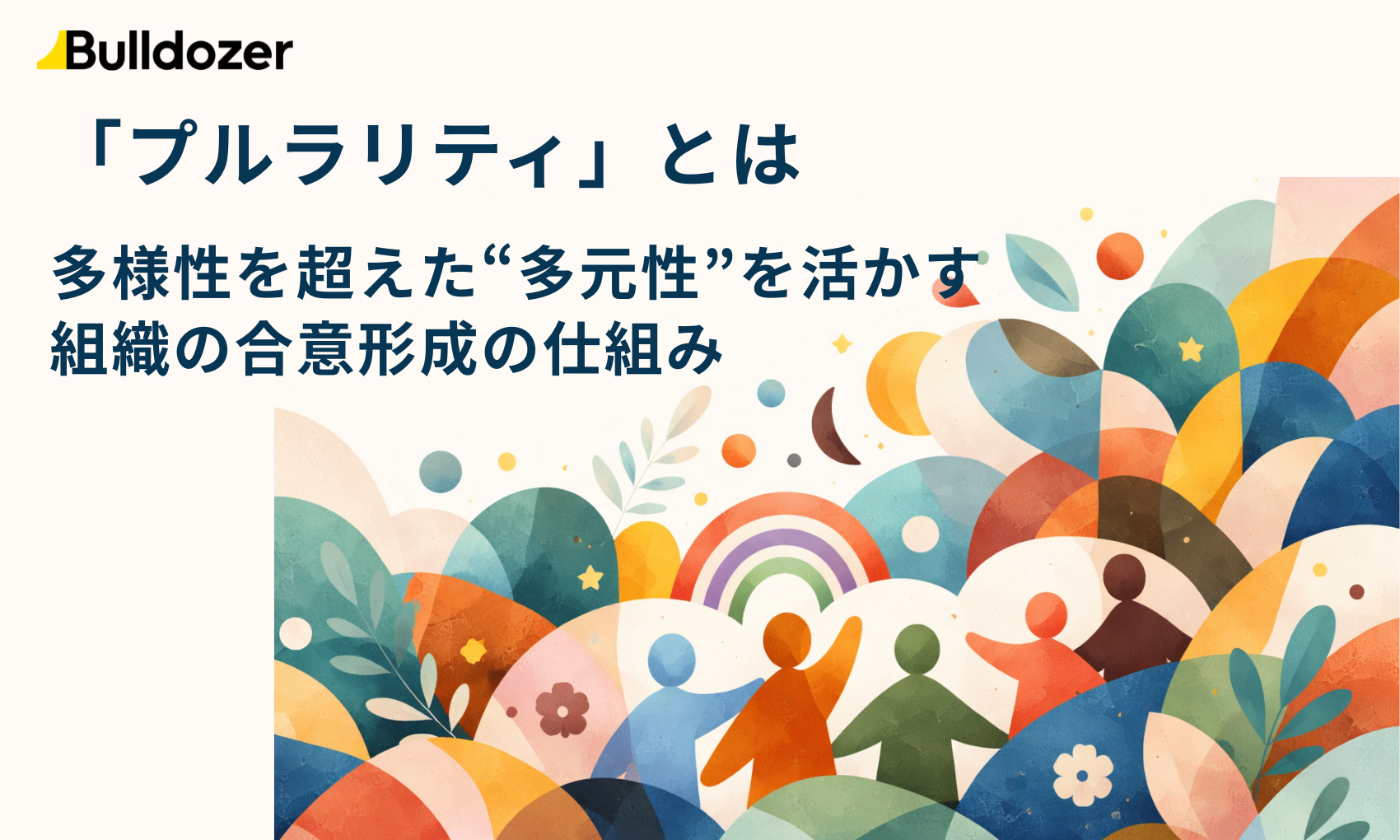「生産性」は誰のためにあるのか?
まず問い直したいのは、「生産性」という言葉の前提です。
企業の利益のため?チームの成果のため?それとも、働く個人の充実のため?
Bulldozerでは、「主体性と偶発性」が生産性の鍵だと考えます。
生産性は“管理されるもの”ではなく、“育まれるもの”であるべきです。つまり、数値で測るのではなく、文化や空気感の中で醸成されるものです。
偶発性は「ノイズ」ではなく「資源」
偶発性は、計画された会議やKPIの外側にあるもの。たとえば、誰かの雑談がきっかけでアイデアが生まれたり、予定外の質問が議論を深めたり。こうした“ノイズ”を排除するのではなく、むしろ歓迎する文化が必要です。
ワークショップ形式の会議では、偶発性が発生します。問いの立て方、空間のレイアウト、時間の流れが、偶然の出会いを促すのです。これは、単なる「会議の形式」ではなく、「創造の場づくり」なのです。
空間が語る「無言のメッセージ」
コロナ渦が明けてから、引き続き柔軟にリモート・在宅勤務の対応を取り入れている企業と、社員に再び出社を促す企業と、両方の動きがあるのをご存じでしょうか?
ここで考えたいのは、「会社」という空間にはどんな情報があるのか?という問いです。
空間は、言葉を使わずに人の行動や思考を誘導します。
たとえば:
◾️ 窓のない会議室 vs. 自然光が差し込むラウンジ
◾️ 固定席 vs. 可動式の円卓
◾️ ホワイトボードの有無、壁の色、音の反響
これらはすべて、発言のしやすさ、思考の広がり、意思決定のスピードに影響します。つまり、空間は「見えないファシリテーター」なのです。
時間の質が文化をつくる
「時間と空間が文化をつくる」という視点は、非常に本質的です。
時間の使い方は、組織の価値観を映します。
たとえば:
◾️ 目的のない定例会議が続く組織は、思考の停滞を招く
◾️ 対話の時間を意図的に設ける組織は、信頼と創造性を育む
Bulldozerのワークショップでは、時間の流れや空間そのものが設計されており、参加者が「考える時間」「話す時間」を意識的に体験します。これは、単なる効率化ではなく、時間と空間を通した文化の醸成の場でもあるのです。
なぜ普段の会議では意見が出ないのか?
この問いは多くの組織が直面する課題です。
その原因は、心理的安全性の欠如、目的の不明確さ、空間の硬直性など、複合的であると考えられます。
しかし、ヒントは「空間にある情報」にあるかもしれません。
たとえば、誰がどこに座るか、誰が最初に話すか、資料の提示方法など、空間に埋め込まれた“無意識のルール”が、発言の自由度を左右しているのです。
ワークショップは「問いを立てる場」
Bulldozerが提供するワークショップは、答えを出す場ではなく、「問いを立てる場」です。
問いが深ければ、思考は深まる。問いが広ければ、発想は広がる。
そして、問いが共有されれば、意思決定は加速する。
このような場づくりは、単なる会議の代替ではなく、組織の思考の質を変える装置です。
生産性とは、こうした「問いの文化」が根付いたときに、自然と立ち上がるものなのかもしれません。
他のおすすめ記事をみる
Contact
資料のダウンロード・
お問い合わせはこちらへ
「アート思考、良さそうだけどピンときてない・・・」「うちの組織にどう適用したらいいかわからない」
そう思うのは自然なことです。どんなことでもお気軽にご相談ください。