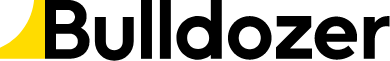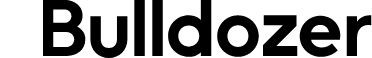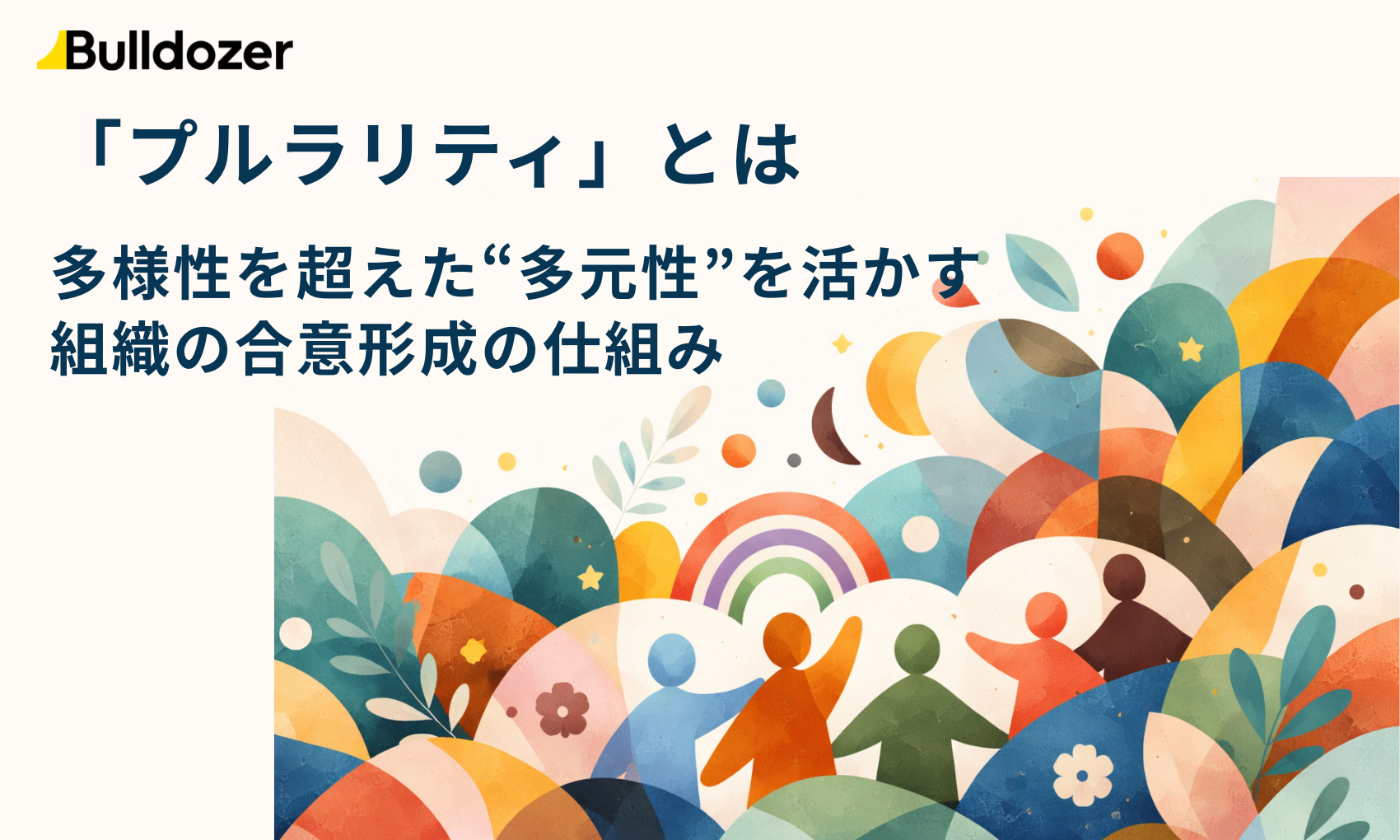AIやシステム化の進展は、企業の人材戦略に大きな変化をもたらしています。
これまで多くの社員が担ってきた「10→100」の業務、つまり確立された作業を繰り返し実行する仕事は、自動化によって急速に減少しています。
この変化は、人事や経営にとって「再配置・育成・採用」という3つの側面で新たな問いを突きつけています。
作業のピラミッド構造の変化と“発想の起点”
企業内の仕事は、大きく3つの層に分けられます。
◾️0→1: 新しいアイデアやビジネスを創出する層
◾️1→10: 生まれたアイデアを形にし、プロジェクトとして実行する層
◾️10→100: 確立された業務を繰り返し実行する層
従来の組織は「10→100」を多く抱えることで安定していました。しかし、AIやRPAの普及によってこの層が縮小する中、企業は“0→1”や“1→10”に比重を移し、構想力や批判的思考、そして創造的対話を中心とした仕事の再設計を迫られています。
ここで問われるのは単なるスキルではなく、内発的な動機を起点とする思考の転換です。
人事が取り組むべき3つの課題 ― 「再配置」「スキル変革」「採用」
1. 再配置の設計:変革の意志を支える環境づくり
定型業務に従事していた社員を“1→10”や“0→1”の領域にどう移すか。
単なる異動ではなく、「能力の開花」につながる丁寧な設計と心理的安全性のある場が欠かせません。
このプロセスには、多様な視点を交わしながら行う共創のプロセスが求められます。
2. スキル変革の支援:思考の余白をつくる
“1→10”を担う人材には、プロジェクト推進力や関係性の質を高める力。
“0→1”を担う人材には、前提を問い直し、未知に踏み出す知的探求心が必要です。
これらは座学では身につかず、Bulldozerが実践するような創造的対話を通じたワークショップによって、社員一人ひとりの「起点(オリジン)」から意味のある革新を引き出す体験が有効です。
3. 採用ポリシーの見直し:価値基準の再定義
採用・評価基準を「作業遂行力」から「構想力・創造力」へ。
「新しい視点を生み出せるか」「共有される物語を描けるか」という独自の価値基準を取り入れることが、持続可能な成長と競争優位性を築く鍵となります。
“0→1”と“1→10”を育てるために ― 組織的学習のデザイン
“0→1”人材は新しい発想を生み出し、“1→10”人材はそれを形にしていきます。
どちらが欠けても、価値創造の循環は生まれません。人事に求められるのは、社員をどの層に位置づけ、どうすれば自律的な組織として機能させられるかを見極めること。
Bulldozerの「アート思考(オリジンベースド・アートシンキング)」は、部署を越えた創造的対話を通じて、社員が自身の存在意義や志向性を再発見しながら、新たな可能性を形にしていくプロセスを支援します。その過程で、個々の動機がチームの知恵へと統合され、社会的インパクトを生む構想が生まれます。
AI時代の人材育成に必要な“思考の再定義”
AIの進化によって「10→100の仕事」は確実に減少していきます。
これからの組織に求められるのは、思考の余白を持ちながら新しい価値を構想する力です。
◾️再配置で社員の内発的な動機を引き出す
◾️ワークショップで洞察の深化を促す
◾️採用で意味のある革新を評価する
これらを統合的アプローチで組み込むことができるかどうかが、今後の企業の未来を決定づけます。そして、その変革を推進する中心にこそ、人事部門があります。
Bulldozerは、社員一人ひとりの起点から未来を描く「アートシンキング」を通じて、組織が描く未来を現実へと変える支援を続けています。
他のおすすめ記事をみる
Contact
資料のダウンロード・
お問い合わせはこちらへ
「アート思考、良さそうだけどピンときてない・・・」「うちの組織にどう適用したらいいかわからない」
そう思うのは自然なことです。どんなことでもお気軽にご相談ください。