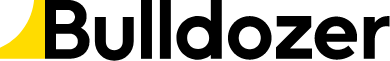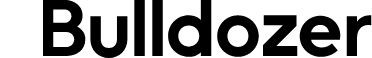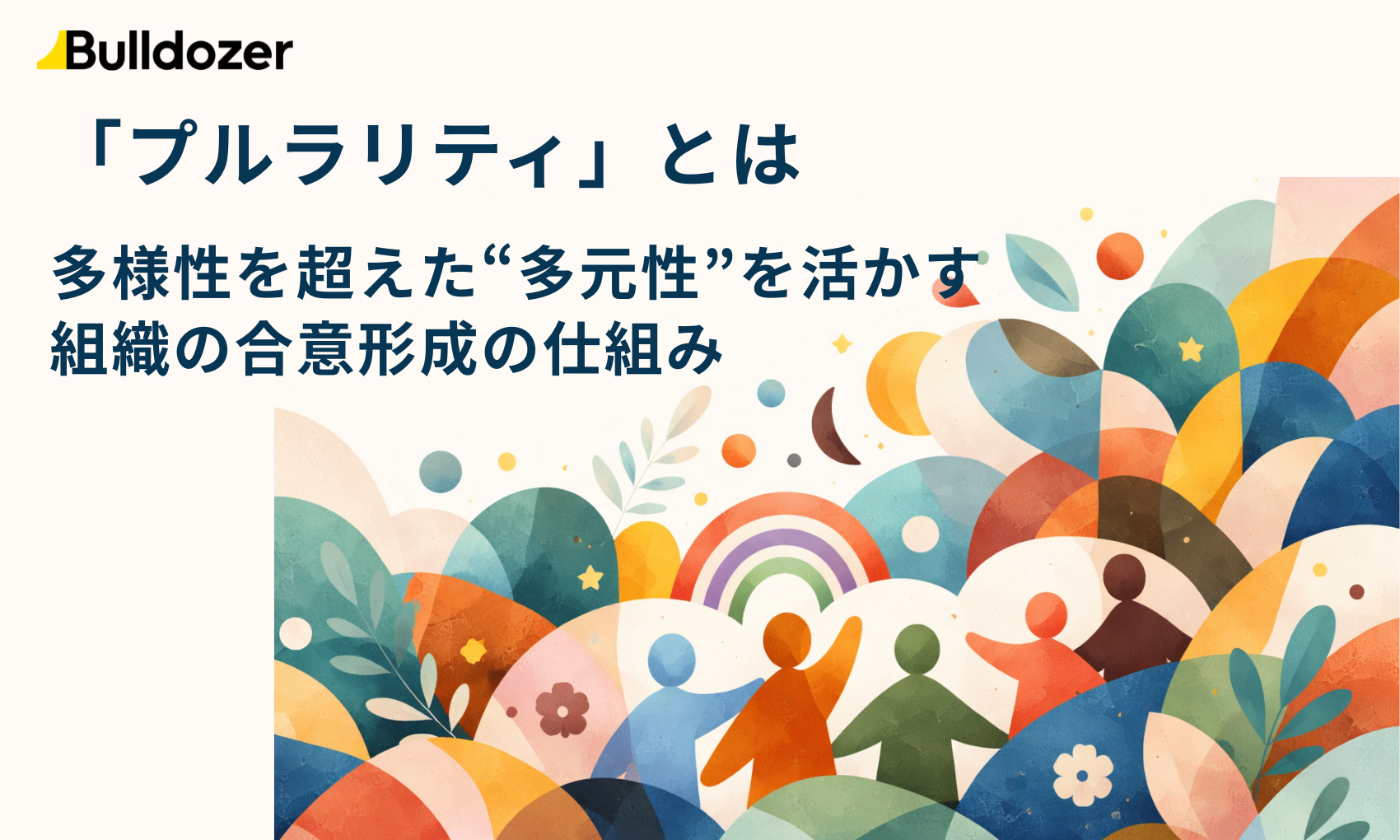デジタルに疲れた脳が欲している“間”と“触感”
スマートフォンやチャットツールが常に手元にある現代、ふと紙に触れたくなる瞬間があります。予定を手帳に書く、思いつきを付箋にメモする、あるいはアイデアをスケッチブックに描く──そんな行為が、不思議と自分の内側に深く潜っていく入口になる。
この感覚に、多くの方が共感しているのではないでしょうか。実際、フィンランドでは一部の学校がデジタル教材から紙の教科書に戻す動きを始めています。これは単なる懐古趣味ではなく、「私たちはどのように思考し、創造するのか」という問いへの真剣な探求とも言えるでしょう。
「問いを立てる力」を育む、アナログな回路
生成AIの進化によって、私たちはかつてないスピードで情報を処理できるようになりました。しかし、AIが得意とするのは“答え”を提示することであって、“問い”を立てるのは依然として人間の役割です。問いの質こそが、思考の深さと創造の原点を決定づけるのです。
Bulldozerでは、この「問いを立てる力」にこそ未来の競争力があると考えています。だからこそ、デジタルの利便性を活かしながらも、あえてアナログなワークショップを取り入れています。たとえば、私たちのプログラムでは、自分の価値観を香りとして調香するワークや、タイムトラベルのように思考の時間軸をずらす「時空間の振り子」など、感覚や身体性を伴う体験を通して、社員一人ひとりの思考に立体性を持たせています。
紙に触れる行為が「内なる創造性」を引き出す
私たちも、ペーパーレスが進む時代の中で、業務効率化を目的に大量の情報をあえて印刷し、そこにマーカーを引いたり手書きで考察を加えたりするというアナログなアプローチを取り入れています。その結果、ただ読むよりも情報の解像度が高まり、チームでの議論も一層濃くなることを実感してきました。
これは、Bulldozerが掲げる「オリジンベースのアート思考」とも重なります。社員が自身の価値観や動機(=オリジン)を言語化し、それを起点に未来を描くことで、今の行動につなげていく。このプロセスを促すには、五感を伴うアナログな手法がとても有効なのです。
「問いの余白」に気づける組織へ
テクノロジーが進化するほど、私たちは人間らしい思考の幅を取り戻したくなる。紙に触れるという行為は、その第一歩かもしれません。そして、その“余白”こそが、部署を越えて本音が交差し、新しい視点が生まれる起点になるのです。
もし、貴社でも「社員の主体性を引き出したい」「創造的な対話を促進したい」とお考えであれば、Bulldozerのアートシンキング・ワークショップがお役に立てるかもしれません。紙とペンから始まる、小さくて確かな思考の旅に、ぜひご一緒しませんか?
他のおすすめ記事をみる
Contact
資料のダウンロード・
お問い合わせはこちらへ
「アート思考、良さそうだけどピンときてない・・・」「うちの組織にどう適用したらいいかわからない」
そう思うのは自然なことです。どんなことでもお気軽にご相談ください。