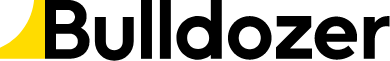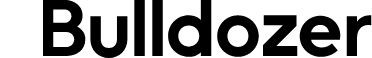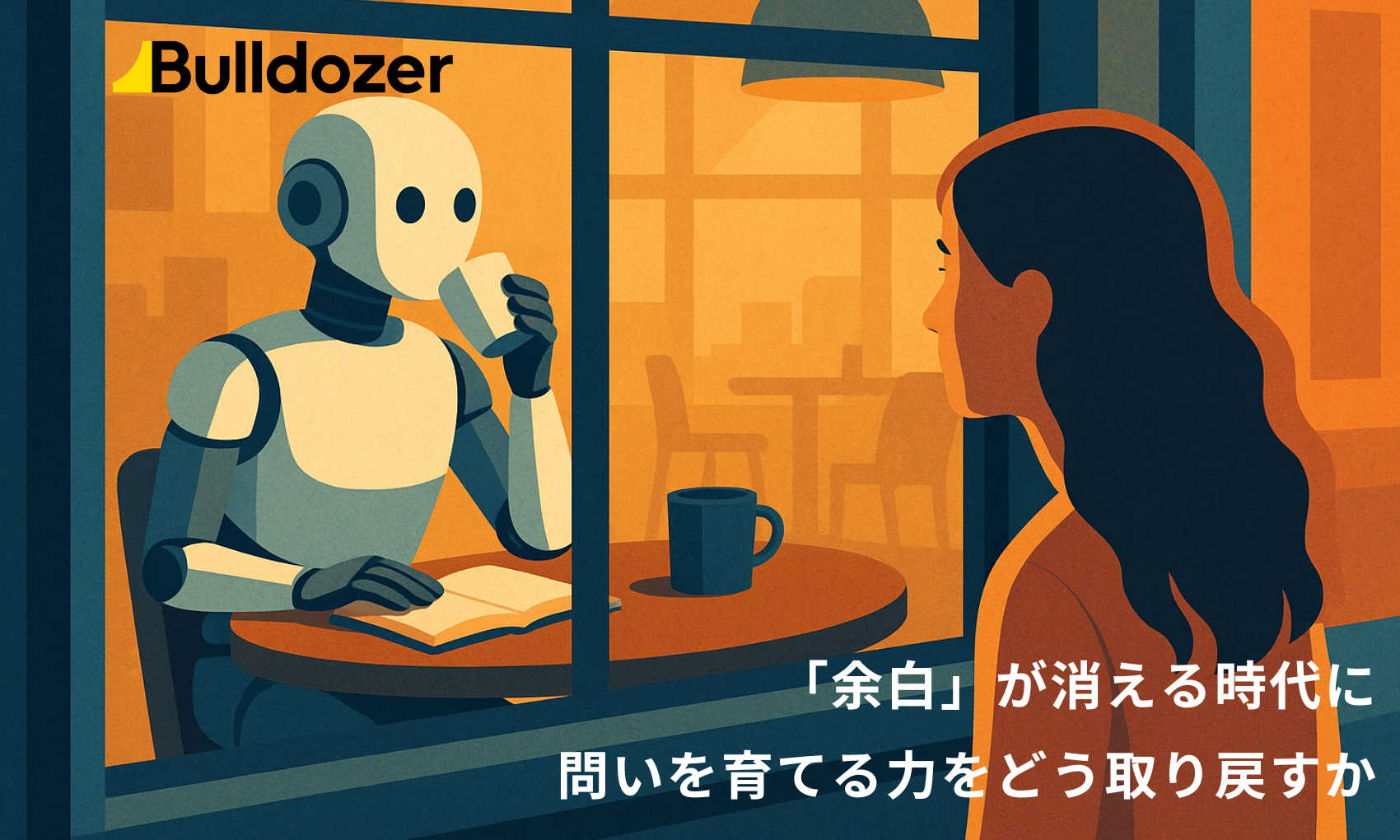
―― AIによって加速する意思決定と、“パーパス”が果たす役割
近年、AIやデジタルツールの発展により、業務の効率化や意思決定のスピードはかつてないほど高まっています。
資料作成、要点整理、思考の下書きまで、ワンクリックで完結する世界。
けれど、その便利さの裏で──「問いを育てる余白」が静かに失われつつあることに、どれだけの人が気づいているでしょうか
「あれ、最近スタバに行ってないな」と気づいた朝
実は、この記事の出発点も、そんな小さな違和感から始まりました。
長年続けていた朝のスタバ通い。毎朝7時から9時の時間は、コーヒーとノートを片手に、自分の中の考えをゆっくりと自由に整理するための時間でした。タスクを消化しながら、「まだ言葉になっていない違和感」や「未整理のアイデア」と向き合う、静かな対話の時間。ところが最近、その時間がかなり少なくなっていたんです。
なぜか? そう考えたときに浮かんだのが、AIの存在でした。
AIによって進む“省略の時代”と、思考の質の変化
AIツールによって、考えるスピードが一気に加速した実感があります。
資料の構造化や意思決定の準備が、以前よりも圧倒的に早く終わる。仕掛かり中のタスクやモヤモヤが減り、「立ち止まって考える必要」が自然と少なくなっていたのです。
でも、それは同時に──問いに出会う機会を失っていたということでもありました。
私たちは、「問いを取り戻す場づくり」を通じて、組織に思考の余白を取り戻す支援をしています。
「なぜやるのか」が見えにくくなるリスク
効率化が進む一方で、現場では「何を」「どうやるか」ばかりが先行し、「なぜそれをやるのか?」という問いが後回しになるケースが増えています。
これから先、2050年くらいまでは大まかな予測ができたとしても、その先の未来は本当にオープンです。
だからこそ、パーパス(存在意義)を自ら描くことが重要になると、日々の打ち合わせでも実感しています。
未来の予測が効かないからこそ、「どこへ向かいたいか」を自ら定める必要がある。
それが、変化の波の中でも迷わず進み続けるための羅針盤になるのです。
パーパス策定や未来構想の対話の場を通じて、組織の軸をつくるお手伝いをしています。
雑談、沈黙、違和感――そこにこそ「問い」はある
私たちBulldozerのワークショップでは、アート思考や参加型ワークショップを通じて、「問い」を発見する体験を大切にしています。
それは何か特別な技術ではなく、むしろ意味のなさそうに見える時間や対話の中にこそ、“問いの芽”が潜んでいると考えているからです。
たとえば、何も決まらなかった会議の沈黙。横道に逸れた雑談。誰かの違和感。そこに、未来をつくる本質的な問いが隠れているのです。
他の組織がどのように問いと出会い、変化を起こしているのかをご紹介しています。
AIにできないことを、私たちはどう育てていくか
AIは、仕事を速くしてくれる。
でも「問いに出会うこと」「意味をつくること」は、やはり人間にしかできません。
今の時代にこそ、立ち止まる時間が必要です。また、パーパスをもとに未来像を描き、この先の指針として持っておくことが大切です。
考えることを急がず、問いに向き合う余白を持つことが、未来を選び取る力につながります。
「問いを持つ力」を育てたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
他のおすすめ記事をみる
Contact
資料のダウンロード・
お問い合わせはこちらへ
「アート思考、良さそうだけどピンときてない・・・」「うちの組織にどう適用したらいいかわからない」
そう思うのは自然なことです。どんなことでもお気軽にご相談ください。