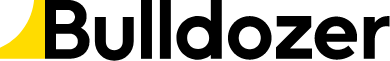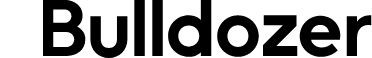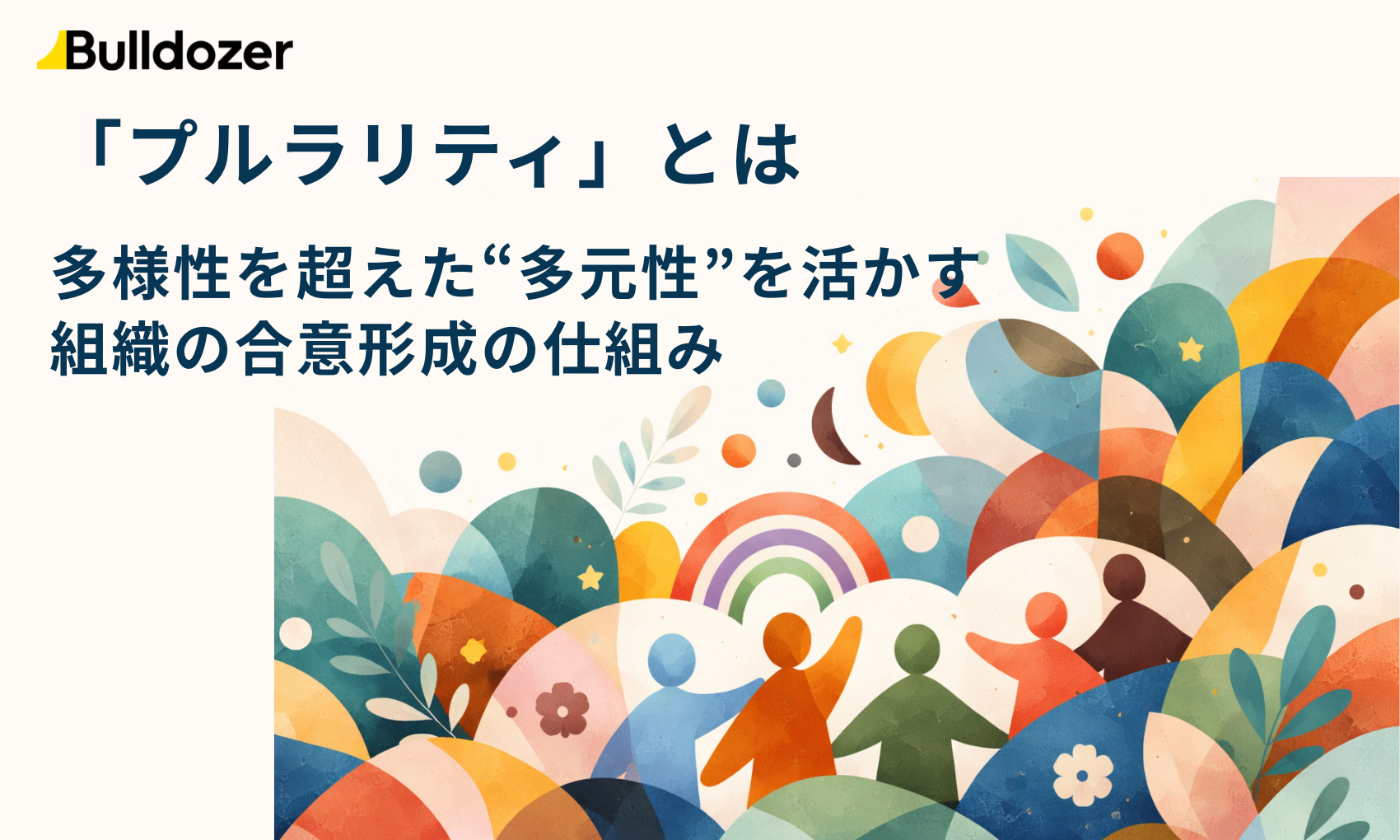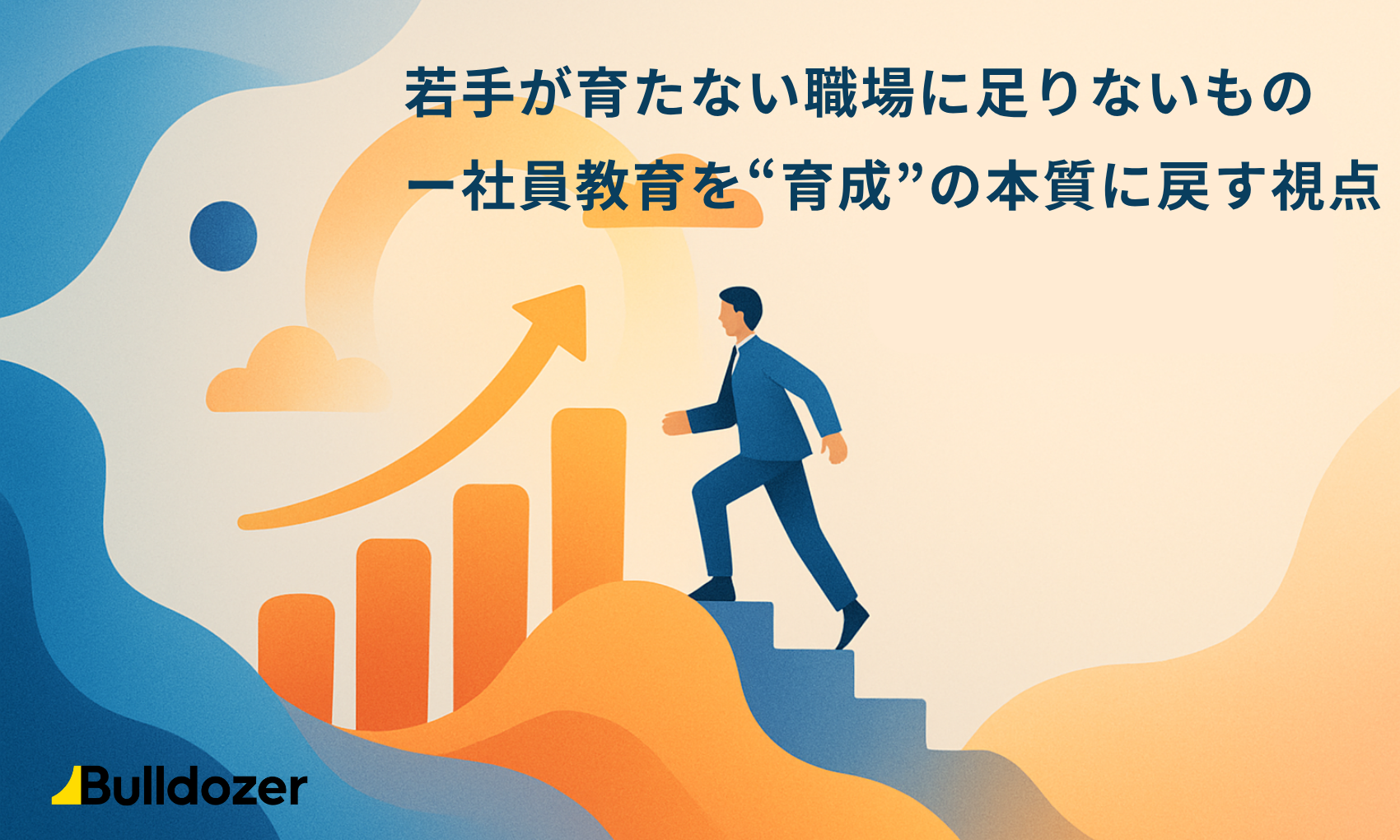
違和感の正体は「なぜやるのか」が伝わっていないこと
「とりあえず現場で覚えて」と言われたまま、戸惑いながら退職を選ぶ若手社員。そんなケースが増えています。確かに、経験からしか学べないことは多くあります。
しかし、何の判断基準も示されないまま、ただ実務に放り込まれる状況では、若手は迷うばかりです。”現場に出せば育つ”という前提が、実は育成の空白を生んでいるのではないでしょうか。
「現場で覚えろ」だけでは育たない
多くの企業では、「OJT=社員教育」と捉えられている傾向があります。しかし、OJTはあくまで手段の一つでしかありません。
実際には、基礎知識や判断の基準となる価値観の共有、内省や対話の機会といった、より全体的な”教育設計”が必要です。OJTだけに頼っている職場では、仕事の意味や全体像が見えないまま業務が積み上がり、若手は“こなす”だけの働き方に陥ってしまいます。
教育の土台は「会社の原点」──MVVとパーパスの共有
育成がうまくいかない本質的な原因は、「パーパスやMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)が社員に共有されていない」点にあるとBulldozerは考えます。
組織の根本にある価値観が伝わらなければ、日々の業務は“意味のない作業”になってしまいます。教育とは、知識やスキルを伝える前に、まず「なぜこの会社で働くのか」をともに考えるところから始めるべきなのです。
Bulldozerの実践──教育は“原点の言語化”から始まる
Bulldozerでは、社員教育の起点を「組織の原点の可視化」と「対話による共有」に置いています。MVVやパーパスを明文化するだけでなく、それを社員が自分の言葉で語れるようにする。そのプロセスを通じて、日々の業務が“目的とつながった活動”に変化します。
こうして育成された社員は、自ら考え、動く力を持ち、単なる作業員ではなく“意味を創る担い手”へと成長していきます。
上司の役割も変わる──教えるのではなく、つなぐ
社員教育というと、若手だけが対象のように思われがちですが、実は上司自身にも学び直しが求められています。特に価値観の共有という観点では、上司がMVVを自分ごととして理解していないと、若手に伝えることはできません。
Bulldozerでは、上司が自身の価値観を整理し、それを若手と“つなげる”ための対話力を高めるプログラムも提供しています。
教育の再定義が、組織を変える
本来の社員教育とは、業務スキルを教えるだけでなく、組織の価値観や文化を浸透させ、自律的に動ける人材を育てる営みです。
Bulldozerのオリジンベースド・アートシンキングでは、組織の原点を起点に、対話と体験を通じて“共有された未来像”を描き出します。そうした教育文化が根付いた組織では、部門や世代を超えて共通言語が生まれ、連携や創造性が自然と育まれていきます。
育成とは、価値観をともに育む営み
若手が職場に定着しないのは、意欲や能力の問題ではありません。教育の出発点である“組織のOS”──MVVやパーパスの共有がされていないことに起因しています。
社員教育を単なる業務研修ではなく、「価値観の共有と対話による育成」へとシフトすることで、人と組織はともに変わっていきます。
Bulldozerのワークショップでは、その変化のきっかけとなる場を提供しています。今こそ、社員教育の本質を見直しませんか?
他のおすすめ記事をみる
Contact
資料のダウンロード・
お問い合わせはこちらへ
「アート思考、良さそうだけどピンときてない・・・」「うちの組織にどう適用したらいいかわからない」
そう思うのは自然なことです。どんなことでもお気軽にご相談ください。